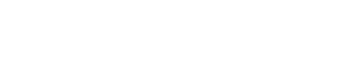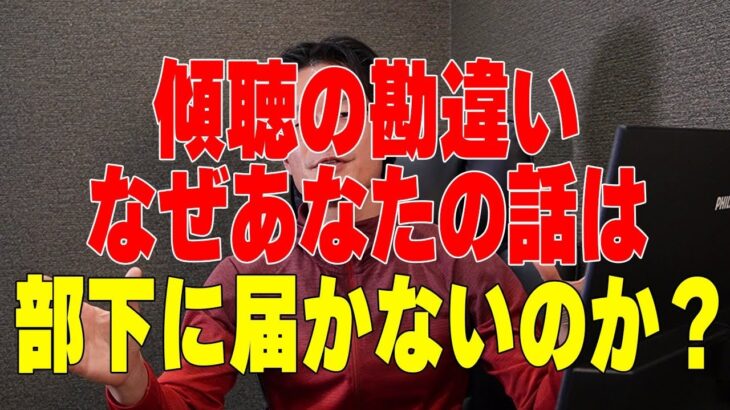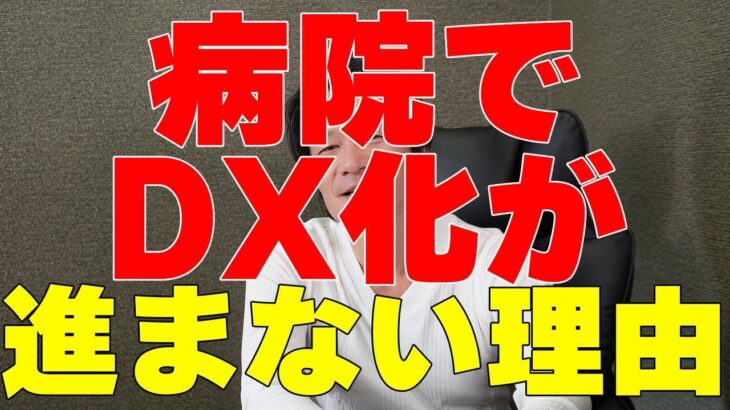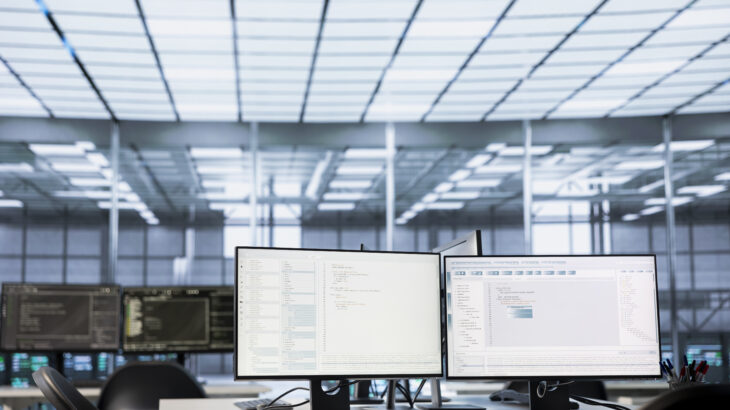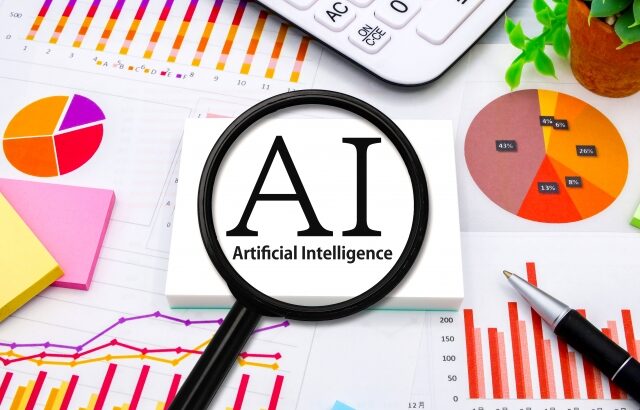「自信過剰気味の管理者がいるのですが、そのせいか、
僕の意向を確認することなくというか確認したと思い込んで、
独断で判断・行動してしまいます。
徐々に現場とのズレやトラブルが増え、職員の士気も低下しているような気がします。
本人はは自信たっぷりな上によかれと思ってというスタンスなので、
指摘もしづらく、どう改善に導けばいいのか悩んでいます。」
先日病院、先代から経営を引き継いだ二代目院長にあたる先生が
ほとほと困り果てたという様子でご相談をくださいました。
確かに自分ができていると思っている人には
正直かなり指摘しづらいですよね。
年上だったりしたらなおのことです。
こういったケースにおける一番の悪手は、
真正面から個人を変えようとすることです。
コーチング等で解釈や認識を変えることは可能ですが、
結構なスキルが必要になってしまいますし、内部でやると角が立つこともあるので、
組織内でやるときは、個人を変える前提で動くのではなく
個人が徐々に良くなる「仕組み」と「環境」を整えていく方がよいでしょう。
その際のポイントは3つです。
① 「仕組み化」で防ぐ(個人に頼らず、ルールでカバー)
特定の人だけに注意しても、本人にできていない認識がないので
おそらくあまり効果がありません。
組織全体で「部下に周知をする時は落とし込み方も含めて上司や関係者に確認を取る」などの仕組みを整えます。
心配のない判断ができる方ができてたら、もちろん判断を任せてもよいのですが、
原則論をつくることで、本人のプライドを傷つけずに自然な形で独断を防ぐことができるでしょう。
② 「成果ベースのフィードバック」(正論ではなく事実で伝える)
「あなたは間違っている」と正論でぶつかるのではなく、
「この成果に至っていない」、「現状こういう状態になっている」と、
客観的な事実や成果に基づいてフィードバックしましょう。
言った言わない、あっている間違っているで言い出すと、
論点がそこになってしまうので本人が聞き入れ辛い状態を作ってしまいます。
③ 「適材適所の配置」(強みを活かし、弱みをカバーする)
適材適所ということでリーダーシップや行動力という強みを活かすために、
「新規プロジェクトの立ち上げ」や「方向性の提案」などの役割に重点を置いてもよいでしょう。
一方で、現場との調整や細かなコミュニケーションが必要な業務は、
別の得意なスタッフに任せることで、組織全体のバランスが良くなるかもしれません。
このように「仕組み」「フィードバック」「適材適所」を工夫することで、
自信家の管理者の強みを活かしつつ、活かすことができるようになります。
個人をなんとかしようとしすぎず、他に似たような人が入ってきたとしても
機能する仕組みを作るチャンスだと捉えて動けるとよいかもしれませんね!
独断専行の方がいらっしゃる場合の参考になれば幸いです!
人事コンサルタント
金森秀晃