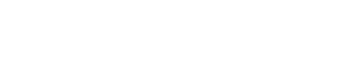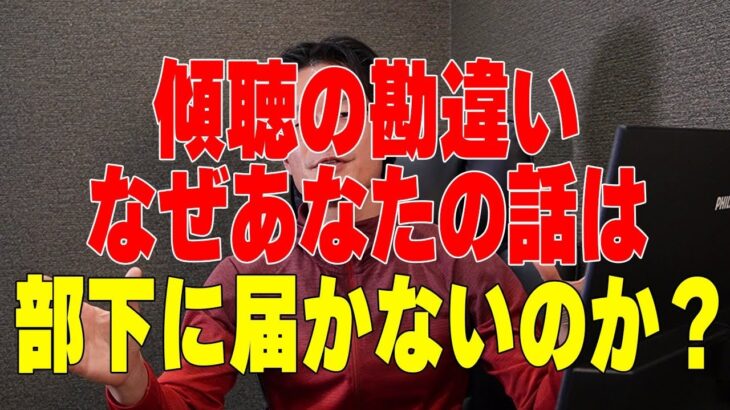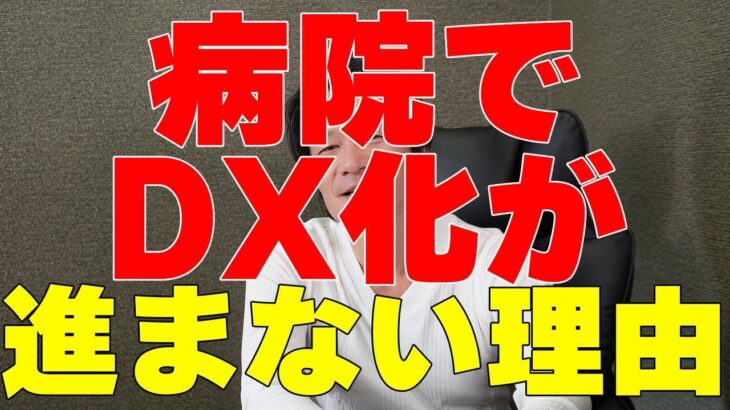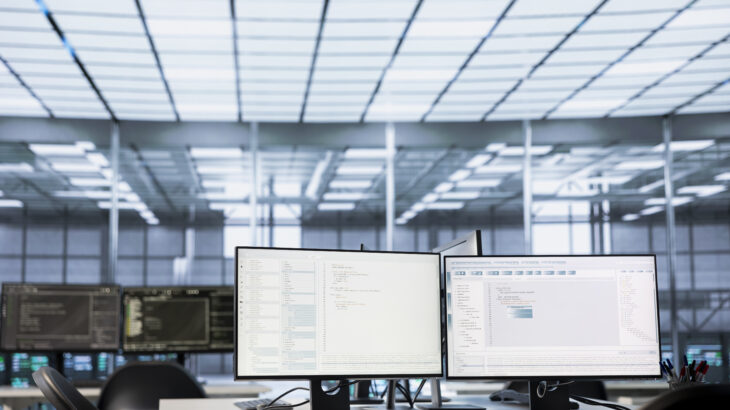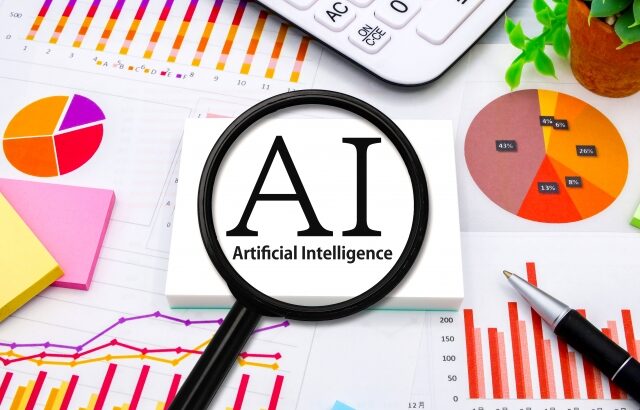「受け持ち患者数が多くてよく働く先生の負担を減らそうと
主治医制からチーム制にしたのですが、逆に有能で当事者意識の高い先生の
負担が増えてしまいました。
形だけのチーム制で責任の所在が曖昧になって当事者意識が高く、
一生懸命な先生に仕事が押し付けられている構図なのだと思います。
主治医制でもチーム制でも結局同じになってしまい、困っています。」
頑張る先生の負担を減らそうと体制を変えたのに、
逆効果になってしまったとなると辛いものがありますよね…
頑張る先生方にも申し訳ない気持ちがします…
ですが、こういったお悩み、最近本当に多いんです…!
なぜこういったことが起こるのか?
それは、釈迦に説法のようなお話ですが、
本質的な問題が解消されないまま、やり方だけを変えているからです。
そもそもですが、パフォーマンスに偏りがあり
受け持ちが多い人、少ない人が生じてしまうのは、
「主治医制だから」ではありません。
多くの場合は「それが許される環境だから」です。
あの先生は優秀だからとか、人気の先生だからとか
色々理由はあがってくると思いますが、
それらはその有能な先生の患者が増える原因になっても、
他の医師の受け持ちが少ない理由にはなりえません。
少なくとも700以上の医療機関を見てきましたが、これは鉄板の事実です。
(感覚値としてもみなさんそうなのではないでしょうか。)
そのため、この問題を根本的に解消していこうと思ったら、
「一人ひとりの役割と責任を明確にし、
それを管理監督する仕組みが必要」ということになりますよね。
それがないまま、主治医制をチーム制にしても、
より責任がふんわりしてしまい問題が解決しないことになるのです。
ということで!
新たな仕組みや枠組みを構築する際、
絶対に抑えなければならないポイントはこの3つです。
・主治医制でもチーム制でもそれぞれの先生に求めたい役割と成果を明確にする
・合意形成が取れた役割やプロセスが守れらているかの管理監督する
・正当な理由もなくそれらがなされていない場合の当該医師へのダメージ(減給や賞与への反映など)を明示する
「罰則みたいなのはちょっと…」とおっしゃる方もいるのですが、
これをやらない限り頑張る先生を見殺しにすることになってしまうので、
経営者としてはしっかりと選択をして姿勢を示すこともある意味責任だと思います。
医師の働き方改革を進める中で主治医制からチーム制への転換などを
進めていらっしゃる医療機関も多いかと思いますが、
その際の参考になれば幸いです。
人事コンサルタント
金森秀晃