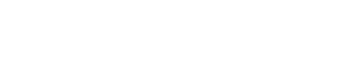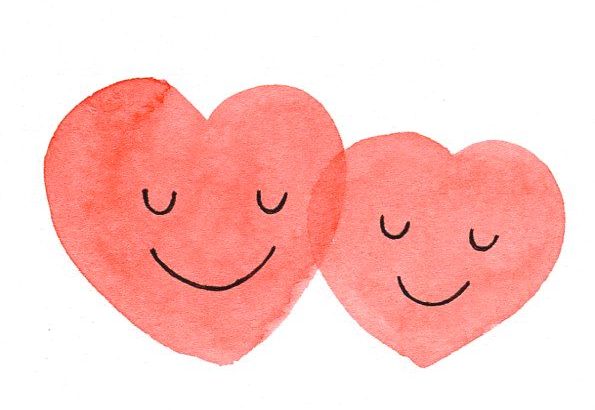こんにちは!
管理部の佐々木です。
本日は私がブログをジャックします。
弊社がある築地・新橋エリアには、平日休日問わず外国人旅行客と思われる人たちがひっきりなしに訪れます。
特に秋は見どころが多い季節というのもあってか、連日とてもにぎわっています。
先日、社用で外出した時のことです。
目的地の道中で歩道橋を渡っていると、外国人旅行客と思しき人が一眼レフカメラを構えて歩道橋の上から熱心に何かの写真を撮っていました。
”写真を撮るほどのものは、この辺にはない気がするんだけど・・・”と思いつつ、何にレンズを向けているのか気になり、その方を見てみると「驚安の殿堂 ドン・キホーテ」だったのです。
私は”えー!こういうのが珍しいんだな、なるほどなぁ”などと思いながらその方の後ろを通り過ぎ、目的地に向かい歩を進めました。
歩きながら先ほどの光景を思い返していると、だんだんと自分がもったいない事をしていたような気持ちになりました。
自分が当たり前すぎてスルーしていることに対して、別の解釈の発見や理解を深めるを見つけるチャンスを逸していると感じたからです。
先述の写真の件であれば
ドン・キホーテのどんな所に写真を撮ろうという動機を掻き立てられたのかを踏み込んで考えてみる(合ってるか否かは別として)と”当たり前の差異”がわかりどう表現すると相手にとって魅力的に映るのか知見が増えるという感じです。
私には”単なるディスカウントストア”であっても旅行客の方からしてみれば”ずっと訪れてみたかった、観光名所”だったかもしれないですよね。
これをZACの仕事に置き換えてみると・・・
クライアントが課題に感じている事(離職、次世代リーダー候補が育たないなど)に対してクライアントの目にはどう映っていて、どこが一番ネックになっているかという事を確認せずに「離職ですか?じゃあこういうことが問題ですよ」という感じで経験則で決めつけて提示し、可能性を探るというプロセスをまるごと省いているような事をしているようなものかもしれません。
自分が考える余地がない、当たり前だろうとおもっていることほどそうじゃない前提で他者から話を聞いたり、思いを馳せるなどして微差があることを知りに行く行動が人生を豊かにしてくれるのかもしれません。
新しいCOAでは”聞く力”と”聞かれる力”の両方を実際に練習できます。
ご興味ありましたらぜひ(^^)/