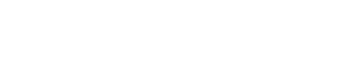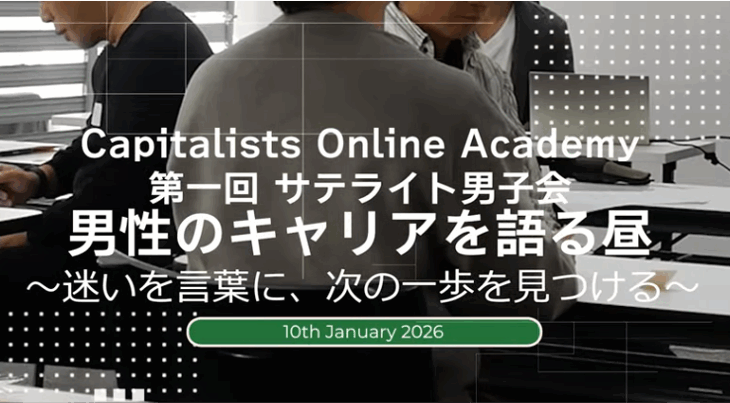「空きベッドがあるのに、患者を受けられない」
「地域包括ケアでよさそうな患者も急性期病棟にとなってしまい、結果稼働が下がる」
「転棟の調整に時間ばかりかかって、気づけば稼働率が落ちている」
病院経営に携わる方なら、こんなお悩みを耳にしたことがあるのではないでしょうか。
ベッドコントロールは病院経営の根幹であり、稼働率の安定は病院経営の数字に直結します。
しかし実際には、思うように機能せず苦労している病院も少なくありません。
原因は色々とあるとは思うのですが、一番は何かといえば
「他職種で本音で話し合えていないこと」
がなのではないかと思っています。
ベッドコントロールが難航する背景には、お互いの立場の違いがあることが多いからです。
医師としては、安全面や急性期における治療継続の必要性を感じており転棟は時期尚早と思っている、
病棟が変わることでの管理・マネジメントが不安だったり、地域包括ケア病棟のケアの質が低いと思っている、こんな場合もあるでしょう。
あるいは患者の納得度の尊重をしきれていないことによるクレームのリスクなどを考えているかもしれません。
(単純に、自分の治療方針に意見されたくないというだけのこともありましたが…)
かたやベッドコントロールを任されている看護師や事務側(経営視点)としては、
医師の医学的見地に基づく判断はもちろん尊重しつつ、
可能な範囲で数値としての稼働率、診療報酬上の効率性をあげていきたいと考えていると思います。
医学的知見についても、先生のおっしゃることもわかるけれど地域包括でも十分にみれるのではというところもあったりすると思います。
まずこのお互いが思っていることをきちんと共有しあえないと解決に向けての第一章にもなりません。
例えば地域包括ケア病棟のケアの質に疑問を感じている先生がいるのならば、どういった点で不安を感じているのかなどを率直に聞かないと
改善のしようもないとなってしまいますし、地域包括でも十分にみれるのではと思う理由や根拠も話し合わなければわかりません。
話し合いの過程で、お互いに経営のことを考えていたのに、
医師側が単純に地域包括ではこれをやっても点数にならないと思っていた、
などの誤解がそこで判明することもありました。
次にその話し合いの中で、病院の方針を明確化していくことが重要になりますが、
それはさほど難しいことではないと思います。
「地域包括ケア病棟へ転棟する基準は何か」
「救急からの受け入れをどう優先するのか」
こうしたルールが曖昧だと、結局は担当医師やその場の調整役の裁量に委ねられ、属人化・場当たり対応につながります。
ここは経営層がリーダーシップを持って「全体最適の基準」を示すことが不可欠です。
そして最後に人事評価制度!
本音をぶつけ合い、方針を決めても、それが職員の行動変容につながらなければベッドコントロールは前進しません。
ここで重要なのが人事評価制度です。(これは医師も例外ではありません)
利益至上主義になれは言いませんが、先生の診療上のこだわりや方針を理解したうえで
場合によっては「稼働率」「地域包括への転棟率」「在宅復帰率」といった指標を評価に組み込むことなども考えられるでしょう。
こうした仕組みを整えることで、先生方も自然と患者の利益はもちろんのこと
「病院経営の視点」からのベッドコントロールについても一緒に考えていただけるようになることが多いです。
(絶対にやってはいけないのは、患者視点を蔑ろにして数字だけ負わせることです。
これでは全員のモチベーションがどんどん低下していきます。)
・本音での話し合い
・病院の方針の明確化
・人事評価制度
この3点セットで多くの経営課題は解決していくことができます。
ご興味のある方はぜひお気軽にご相談ください。
人事コンサルタント
金森秀晃