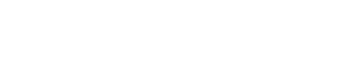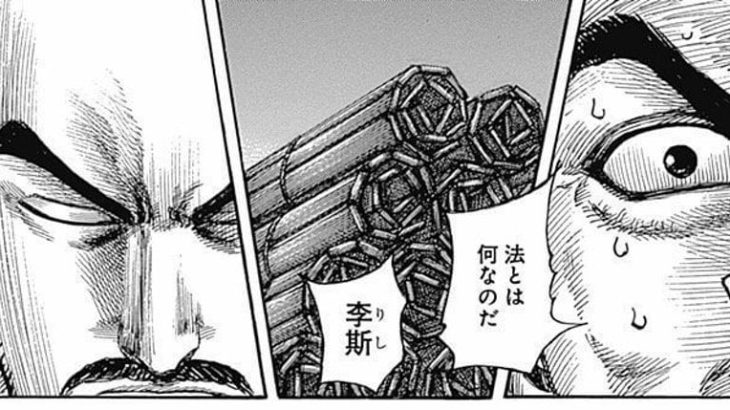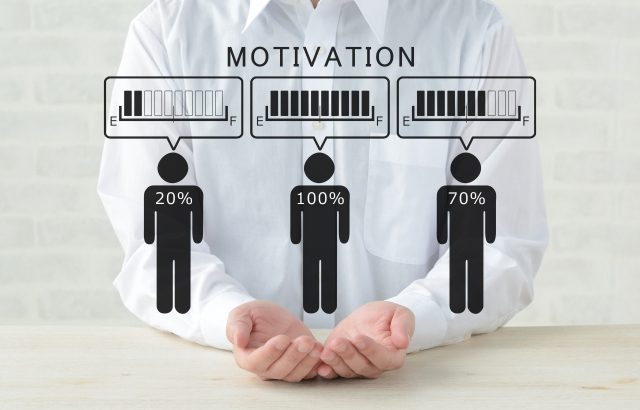同一労働同一賃金や今後の経営を考えた時にということで、
ジョブ型人事制度を検討される法人様が非常に増えてきています。
ただ、現状まだ日本社会全体がジョブ型に馴染んでいるとも思えないので、
一法人だけで完全なるアメリカ型のジョブ型を追求しても、
あまり馴染まないことも多々あります。
(そもそもまだ新卒一括採用ですし…!)
雇用の形がメンバーシップ型を引きずっているのに、
人事制度だけジョブ型にしてしまうとどこかで歪みが生まれますので、
そのバランスをとって中間をとりつつ、徐々にジョブ型に移行していく
素地を作っていくことが重要なように思います。
さて、その中で、最もよく伺う質問ですが、
形骸化せずに機能し、進化し続ける評価制度とはどのようなでしょうか?
というものです。
その特徴は…
評価基準そのものがマネジメント指標、
マネジメントツールになっていること!

どういうことか、実際の等級制度を見ながら考えてみましょう。
▼等級の総括イメージ
※ わかりやすくするため、単線型モデルを想定しています。
ステージ5 複数のチームのマネジメントができるレベル(部長レベル)
ステージ4 1つのチームのマネジメントができるレベル(課長レベル)
ステージ3 マネージャーのサポートと部下指導ができるレベル(主任レベル)
ステージ2 プレーヤーとして一人前のレベル(中堅職員~ベテランレベル)
ステージ1 指導のもと通常業務を遂行できるレベル(新人職員レベル)
▼その中で「報連相」において期待するレベル
ステージ5 新たな解決策を獲得するために常に進化し、素早く学びを共有する
ステージ4 課題をクリアにする支援ができる/相談しやすい環境づくりができる
ステージ3 人の相談したいことを明確にする支援ができる
ステージ2 相談したいことを明確にできる
ステージ1 混乱している状況を報告できる
例えばですが、この場合、新人にはまず
混乱している状況を正直に話すことが重要な役割だと示すことができ、
ステージ2のように相談したいことが明確でなかったからといって
評価が下がるようなことはありませんよね。
ステージ2の形にいけるように、こうしていこうと段階を作って指導することができます。
また、ステージ4にいる人が、ステージ2のように相談したいことを明確にできるのは当たり前。
それを支援したり、環境づくりをするのがあなたの役割だと示すこともできます。
このくらい簡潔に等級制度(それがそのまま評価の指標になります)が
まとまっていると、非常に指導がしやすいですよね!

評価制度は処遇を決めるためのものではなく、
あくまでも育成のためであり、成果に必要な行動をとってもらうためのものです。
それを想定した等級制度や評価制度を構築していきましょう。
是非、参考になさってみてくださいね!
人事コンサルタント
金森秀晃