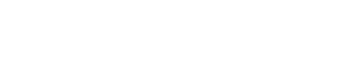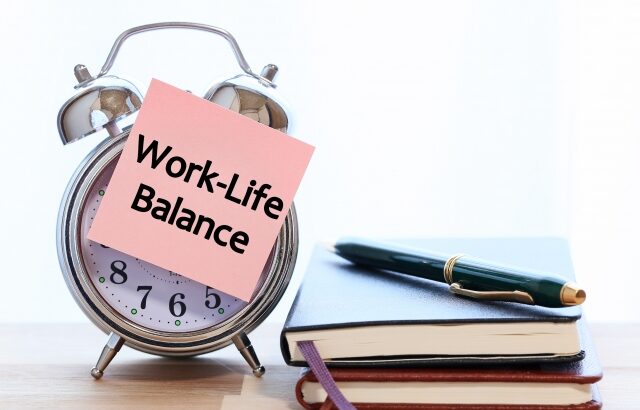「病院の経営は入院数(ベッドの稼働率)から考えても救急を増やす他ない、
ということはわかっているのに、受入数が一向に伸びない。どうしたらいいんだ…」
このようなお悩みを抱える経営者の方は少なくないのではないでしょうか。
みなさんはこうしたとき、まず何をすべきだと思いますか?
私の意見は…
徹底した要因分析
です!
月の推移や昨年との月ごとの対比などの数字分析はもちろん
その数字の変化を取り巻く人間の心情や関係性などを徹底して把握することが重要になります。
例えばですが、救急の件数が落ちている理由を考えてみましょう。
ざーっとあげるだけでもこんなにたくさん理由が出てきます。
(他にももっとあると思います)
・立地的に取り合いになっている
・非常勤の当直医が自分の専門以外全部断ってしまう
・救急医のさじ加減で受け入れ可否が決まってしまい取りこぼしが発生
・受け入れても受け入れなくても自分の待遇変わらないから診ない
・急性期病棟満床で無理があるから受け入れない
・救急担当の医師が病棟看護師と折り合いが悪く、面倒になっている
・受け皿になりうる病棟と救急医の折り合いが悪い
・救急の医師と看護師の仲が悪くて機能不全を起こしている
・高圧的な医師がいて消防が敬遠状態になっている
こうしたものはまず解決策を模索するよりも、
これらの要因分析をしっかりとやりきることで、
ほとんど解決したも同然の状態に持ち込むことが多いのです。
例えば「非常勤の当直医が自分の専門以外全部断ってしまう」が、
救急件数が減っている主な原因だとしましょう。
多くの場合これに対して
「救急とってくれたら~円のインセンティブがつきます」
「初期対応だけして、必要なら転院を勧めてください」
などの解決策を用意します。
これも悪いことではありませんが、根本改善に繋がるかは不明です。
大事なのはもう1つ、2つ原因を掘り下げること。
なぜ専門外のものを断りたくなってしまうのか?
→自信がなくて診断できないかもだし、責任を取れないと思うから
→コンサルできる先生も不在だと怖くて受け入れられないから
→先輩も断っていたし、自分の力量に合わせてでいいと思っていたから
→自分にとってはリスクなだけで何も得られるものがないと思うから
→インセンティブあればとるのかと言われれば、あまり変わらないと思う。
なぜなら一番は理不尽な訴訟が怖いので。
ここまで聞いて…
→どういう状態だったら救急車を受け入れられるか?
→受け入れなければいけないラインを明確にしてもらって、
すぐ経験のある先生や専門医にコンサルできれば…
となればもうやることは明確ですよね。
こういった案件を機に、
非常勤の先生向けに専門外の初期対応について
レクチャーすることにした病院もありました。
「うちにいたらどこの病院からの引っ張りだこの先生になれますよ(笑)」
とおっしゃっていたのも印象的でしたね。
対策を考える前に、まず要因の深堀りを!
救急件数に限らず色々なところで言えることかと思いますので、
ぜひ「解決策先行」になっていないか、確認してみてくださいね。
人事コンサルタント
金森秀晃