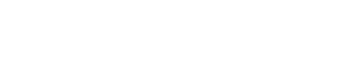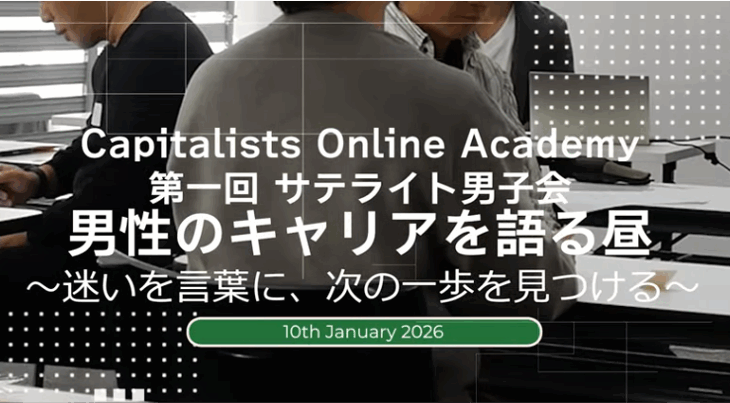ある外科医の先生のポストが、
現場で成果を出すプロフェッショナルの本質を突いていて、
思わず目を奪われました。
手術が遅いのは「慎重だから」でも「丁寧だから」でもない。
思い切って切っていいところと、慎重に進まないといけないところの区別がついてないからだ。
ようは解剖の理解が甘いという事。
解剖を深く理解すれば、丁寧に手術しても手術時間は結果として、短くなる。
— DoDoc (@dkoumon) December 13, 2022
これはあらゆるプロフェッショナルの現場に通じる話ですよね。
例えばですが周りにこんな方はいませんか?
・議事録を漏れなく書こうとしすぎて、
時間もかかり、肝心の意思決定事項や宿題がよくわからない人
・本来、意思決定のキーパーソンに話を通しておけば済む話を
全員に根回ししようとして、関係の薄い部署や上司にまで
「一応」相談をして回り、意思決定を遅らせる人
・どうでもいいこと(相手が望んでいない、気にならない部分)に
拘りをみせて異様に時間を費やしてしまう人
業務の遅さや非効率を「”慎重””丁寧”だからしかたない」と
真剣に思い込んでいる人も少なくないかもしれませんが
そこは一考の余地があると考えてもらえるようにしたいですよね。
そういう方に、ぜひ試していただきたいのがこの思考習慣。
「センターピンはどこか?」を毎回問うという思考習慣です。
これは「ここさえ押さえれば仕事が早く、楽になる」というポイントが
どのような仕事にも必ず存在しているという事実を知り、
そこを見出そうというエネルギーを生む魔法の問いかけなのです。
重要なのはセンターピンそのものではなく、「センターピンを見出す技術を身につけること」です。
状況や登場人物が変わればセンターピンは変化するので、そこに画一的な答えなどないですし、
その瞬間の最高の答えがあったところで次の瞬間には別のものになっている可能性もあるからです。
(そもそもそこに画一的な答えがあるなら、誰もが知っているという意味でそこまで価値がないものかもしれませんよね)
もちろん、業務の初期段階で「よくある無駄」や「気をつけるポイント」を示すことはできますし、
上司であればそれはやるべきでしょう。共通する構図や型を教えるのも重要だと思います。
ですが、それをもとに見極める力を身につけるためには
その構図を頭に入れたり、それを実践で練習して精度を高める訓練が必要です。
組織としてそのポイントを形式知化することも必要だと思いますが、
それがないから動けません、できません、やりませんというのは
社会人としては戦力外通告ものです。
(自分のことだとなんとなく気が付かないかもしれませんが
後輩がそんな事言いだしたら困るなと言うのはわかると思います)
そしてその形式知化する能力こそが、最も市場で評価される能力であり、
それが誰にも奪われない財産になりうるのに、その機会をみすみす放棄していることになってしまいます。
もったいないですよね。
だからこそ一番効率がよいのが
「この仕事のセンターピンはどこか?」と問い続ける習慣なのです。
それが、ただ丁寧な人と、信頼されるプロフェッショナルの違いを生みます。
迷ったときこそ、構造を見て、急所を押さえる努力をしてみる。
そして、急所を外している自分に気づき続ける。
その意識と気付きの連続性が、未来の自分を楽にしてくれるはずです。
私もまだ道半ばですが、センターピンを見抜く力を卓越させていき、
一緒にどんどん楽になっていきましょう!
人事コンサルタント
金森秀晃