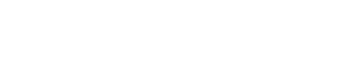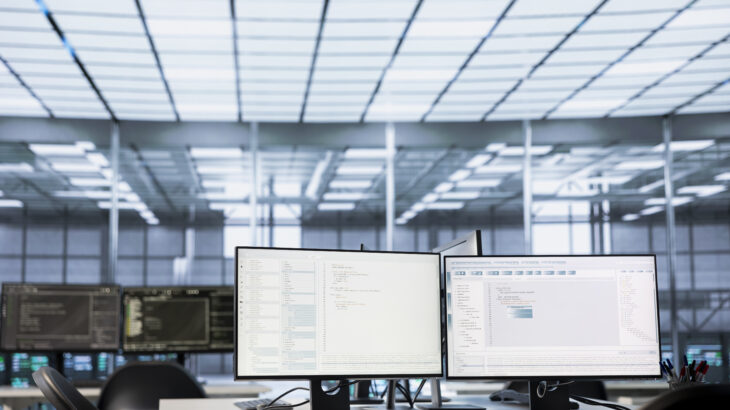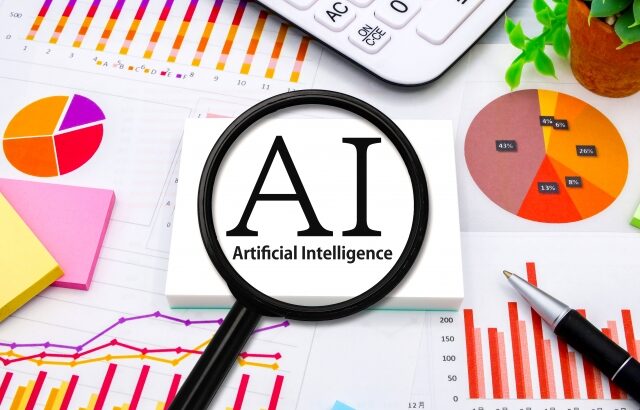みなさんは「ファーストペンギン」という言葉をご存じでしょうか?
有名な言葉なのでご存知の方も多いと思いますが、
天敵がいるかもしれない海に、最初に飛び込む勇気あるペンギンのことです。
ビジネスの世界では、前例のない挑戦し先行者利益を獲得する人のことを指します。
このファーストペンギンが組織改革において大きな役割を果たすことに疑いの余地はありませんが
「組織」を動かすのは、最初の一羽だけではありません。
重要なのは最初の一羽を見て「自分も行こう」と飛び込む、「セカンドペンギン」の存在なのです。
病院という組織は、生命を預かる責任の重さや、専門職が多く集まる職場という性質上、
どうしても「前例」や「安全性」が重視され、新しい取り組みに対して慎重な空気が流れがちです。
どんなに優れた改革案でも、最初に手を挙げた職員(=ファーストペンギン)が孤立すれば、変化は続きません。
(コンサルティング会社に依頼した経営改革プラン等がなかなか形にならないのもこれが原因であることが多いですね)
だからこそ、病院の経営改革において重要になるのは「私もやってみます」と後に続く人の存在です。
セカンドペンギンが現れることで、
「あ、やってもいいんだ」「自分も加わっていいんだ」と、周囲の空気が少しずつ変わり始めるからです。
そして、三羽目、四羽目と続く仲間が現れたとき、はじめて「現場が動く」瞬間が訪れます。
そういう意味では、病院の経営改善、経営改革において最も重要な課題は
「セカンドペンギンを育てること」!
と言えるのではないでしょうか。
トップは組織の方向性を示す立場として、ときに自らファーストペンギンの役割を担うこともあるでしょう。
しかし、それだけでは十分ではありません。
現場、とくに職場長クラスに“二人目”を生み出し、その芽を育てることが重要です。
例えば
・変革マインドをもった職場長を育てる
・小さな挑戦を積極的に評価する仕組みをつくる
・「応援する姿勢」を見せた職員にスポットを当てる
・新しい動きに対して冷笑するような空気を許さない
・失敗しても挑戦したことを称える文化をつくる
これらは、現場にセカンドペンギンを生み出す土壌になります。
そうはいっても、これも言うは易し行うは難し。
一筋縄ではいかないのも事実ですよね。
ですがご安心ください。
弊社では自然とそうした人材が育つ再現性の高い経営改善モデル(CABA-Sモデル)を
20年以上の病院コンサルティング経験を経て開発してまいりました。
組織を動かす仕組みや土壌づくりについて
「やってはいるけど、なかなか変わらずで困っている…」
「手詰まり感を感じている…」
という方はぜひお気軽にご相談ください。
モデルに沿って組織を動かしていけば必ず変わりますので、
仕組みの力で、トップの意向を汲んで動いてくれる”セカンドペンギン”を育てていきましょう!
人事コンサルタント
金森秀晃