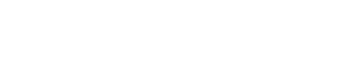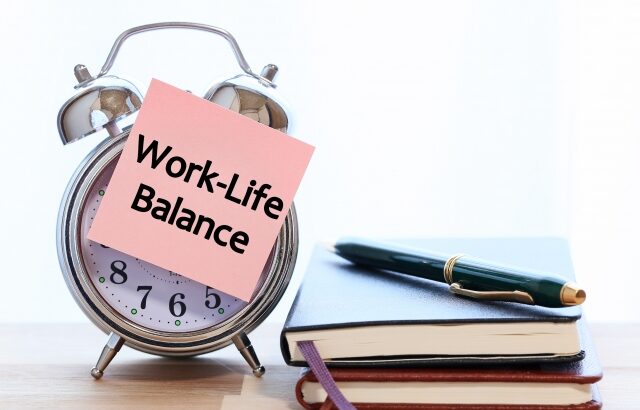6月に入り、異動や新人の配属などで慌ただしかった日々も
少しは落ち着いてきたなという方も多いかもしれませんね。
特にこの時季は、やるべきことを伝えてもなぜか自発的に動かない新人に
頭を抱える方のお話をよく伺います。
「最初は指示が大雑把過ぎたかな、任せる範囲が広過ぎたかなと思って
手順を細分化して示したり、範囲を狭めて指示を出して見たのですが、
あまり変わらなくて・・・。プロ意識なさすぎでしょ!と激を飛ばしたくもなるんですが
グッとこらえてます。」
上司としては切実なお悩みだというのが痛いほど伝わってきますね。
このような現象が起こる要因は色々とありますが
イメージとしては「勉強しなさい!」というお母さん(上司)と、「また言ってる」とやらない子供(部下)の構図を思い出してみるとわかりやすいかもしれません。
代表的な要因をふたつ挙げると
①部下が未来の認識をできておらず、上司の話が一方的な話と捉えてしまう
やったらどうなるか?とやらなかったらどうなるか?の両方を認識させておくことは、
上司の話を”一方的”だと感じさせることを回避してくれます。
上司の立場としては、とにかく進めて欲しいのが先立ってしまいやらなかった場合の話を飛ばしがちかもしれませんね。
②同じことをやるにしても、部下に自己選択感が与えられていない
やった場合・やらなかった場合、両方の未来を認識出来ていなければ、
上司から言われたことはどんなに正しくても負荷と認識されてしまいます。
というのが考えられます。
これらふたつを解消するには
・やったどうなるかを伝えた後に、部下にやらなかった場合どうなると思うかを問い、答えさせること
・自分でやると選択&決断させる(やるべきだよねとコンセンサスをとる)こと
がポイントです。
こうすることで、上司側の問いかけがなくとも
次第にやらなかった場合の不利益を考えることができ、
避けたいことがあったとしてもいやいや・・・と自分で思い直し
自らに負荷をかける(未知のことにトライするなど)ができる人材になっていきます。
今動かないのは、今のことだけで判断をしてしまっているからかもしれません。
そうかもしれないけどお客さんは待ってくれない
仕事ではそんな悠長なこと言ってられない
本当にごもっともだと思います。
育成とは未来を楽にするための、先行投資みたいなものかもしれません。
部下たちに目の前のタスクをただこなさせるだけではなく、
未来を見据えて自発的な人材を増やす、そんなビジョンも持ちつつ
攻めの育成をやっていきたいですね!
人事コンサルタント
金森秀晃